「学校英語にいま何が」大浦暁生・阿原成光編(三友社出版)(1982年)を購入した。
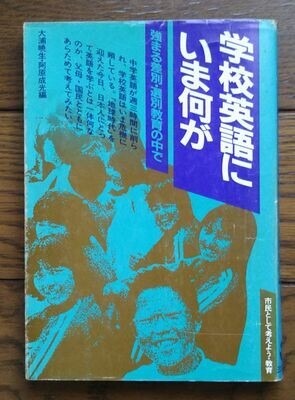
「学校英語を語ろう! <市民として教師として>」と題する國弘正雄さんと小田実さんの対談は読みごたえがある。
芝田進午氏の「わたしにとっての外国語 -国際連帯の手段として」は、おそらく芝田氏の「教育労働の理論」(青木書店)(1975)の「国際連帯と外国語教育の改革」というすばらしい論文と内容的に重複するものだと思う。
斜め読みだが、銀林浩氏(明大教授・数学)の「わたくしにとっての外国語教育」がたいへん興味深かった。
もともと、中学時代に外国語を学ぶとしたら、これは目的意識的に学習する以外にやりようはありません。母国語のように、「生活の中で耳で聞きながら自然に」というわけにはいかないのです。目も口も指も使って、そして何よりも頭を働かせて学ばなければならないものでしょう。それができないなら、外国語の学習などやめてしまえばよいのです。やるならある程度集中してやる以外にはありません。
(中略)
わたくしが言語というものに対する関心を植えつけられたのは、この先生(引用者注:戦争末期の旧制中学校の先生で伊能忠敬の直系の孫。教科書は三省堂のKing's Crown Reader。)のおかげだと思います。ともかく、言葉に論理的構造があるなどということを初めて知ったのは、外国語学習のおかげです。そして、言葉を無意識にではなく、意識して正確に使うという習慣を身につけたのもそのせいです。国語は内容本位、つまり文学であったので、国語学習からはそうした反省的な知識や態度は養われようがなかったのです。
だから無論、外国語といっても、訳読と英作文が主体で、話したり聞いたりなどということはやりませんでした。つまり、言語活動ではなく、教養としての外国語だったわけです。(中略)
わたくしは今日、こうした教養本位の外国語がよいとは決して思いません。第一、現実に外国へいったときにまったく役に立たないからです。一九七六年五月四日、わたくしは羽田をたっていきなりパリのシャルルドゴール空港に降り立ちました。(中略:フランス語・英語・イタリア語・スペイン語でのそれぞれの経験と苦労話に簡単に触れる)
この体験から、われわれが受けた「読む書く」外国語つまり文語と、「話す聞く」外国語つまり口語の学習形態はまったく別物でなければならないと確信するにいたりました。文語の方は、教養の外国語でもよいが、口語の方は要するにそのシチュエーションに置かれなければダメだということです。といって、わたくしはオーラル・メソドを支持するわけではありません。八年ほど前、長男が中学二年のとき、オーラル方式の英語の授業を一度みたことがあるのですが、週四時間だけ、英語だけでやりとりする授業はまるで<箱庭>のようなもので、その非現実性にはただただあきれるばかりでした。中学生を集団で、一週間のうち一か月なり隔離して特訓するならまだしも、オーラル・メソドは今の授業形態ではまったく意味がないと思ったものです。
今の授業形態なら、われわれが受けたような教養英語の方がまだしもましだと思います。ともかく時間をかけただけ何がしかの習得分があるのですから、わたくしが、広い意味の論理的思考というものを学んだのは、数学でも国語でもなく、英語からでした。とくに、翻訳語である抽象概念の意味を本当に理解するのに、外国語の教養は欠かせないでしょう。
(中略)
いずれにしても、外国語の学習は中途半端ではダメです。それは、数学の学習や器楽の習得と同じように、秩序立てて集中的にやらなければ効果は期待できないものだからです。
そういった意味で、もし英語をやるなら、四時間でも不十分であって、少なくとも中学一、二年は五~六時間をあてるべきだと思うものです。
(p.157-p.161)
中学教諭の梅津通郎氏の「社会科は英語に強い子を求めている」と題する論稿も「社会科も英語も世界を学ぶ」として「英語は毎日世界を学んでいるのです。ここに私は英語科と社会科の接点をみます」と書いている。また「歴史教育と英語」として、「ことば」の重要性を指摘している。