「学校英語を語ろう!<市民として教師として>」 対談/國弘正雄/小田実(1982)
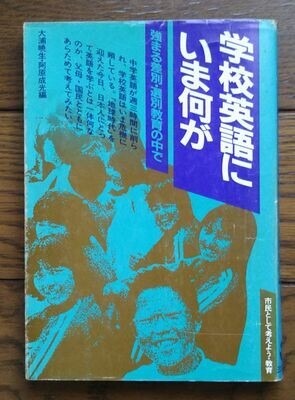
「学校英語にいま何が」の冒頭のほうに収録されている國弘正雄氏と小田実氏の対談がすこぶるおもしろい。
たとえば、小田氏の「特権階級」「庶民」の立ち位置。
(小田)…村の青年団は何もわからないから神がかりになって「軍国主義万歳」を言う。ものを知っている人は、特権階級としてゴルフをする。アメリカにも行き、英語もしゃべれる。ギリシャ語も知っている。ラテン語も知っている。庶民の側は何もわからないから軍国主義と一緒になる。それが東条を支えたり、日本軍国主義を支えていくわけです。(略)
僕が大学に行ったときに、ギリシャ語をやっている人は全部特権階級だよ。私の教授たちは全部特権階級の出ですよ。たとえばオックスフォードに留学していたり、ケンブリッジに留学していたり。私の先生は、オックスフォードに留学したとき、ちゃんとバトラーがついている寮ですからね。彼は確かに学力あるわけ。それに庶民の側が負けまいと志は大きかったが、うまくいかなかった(笑)。
英語のほうは、これは書くことは知っていたんですけれど、しゃべるほうは惨憺たるもので…。「何でも見てやろう」とも書いたけれど実際に英語社会に入ったのはアメリカへ留学してからでしょう。留学を終えてからアジアを回ったりして、今度は第三世界の英語とつき合う。それからベトナム反戦運動を始めて、いやおうなしに英語で国際連帯がもたれていきますね。第三世界に入っていくと、結局使うのは英語しかない。そこでもう一ぺん英語について考え直しを始めたのは、今から十五、六年前じゃないですかね。(p.36-p.37)
世界の言語の社会的・政治的状況については、「根本的には、イギリス帝国主義が全世界を制覇しているという抜きがたい歴史的事実がある。あるいは全世界が多かれ少なかれ英語をやる。それはとやかく言ってもしょうがないと思うのです」(小田)と、基本的政治状況をおさえながら、「たとえばアラブの東京にいる人たち、PLOの人たちと会いますと、彼らは自前の英語なんです。つまり、もう少し年とった世代は非常にうまい英語をしゃべていたんです。ところが若い世代はそううまくない。年とった世代は、非常に植民地化の強いときの連中で、これは非常にうまい英語をしゃべる。それがいやだということに一ぺんなって、全部アラブ語でやれというふうになりながら、アラブ語で全部やると全世界に通じない。しかたがないからもう一ぺん英語をやる。一ぺん自国語に還元して、もう一ぺん共通の言語がないものだから英語をやるという形が、今強い形であるのじゃないですか。私は、そういう英語を自分の英語として考えたいと思っているのです」(小田)と、現状について明快な認識をもたれている。
そのうえで、どうするか。どうしたらよいか。
たとえば、ひとつの解決策である「自前の英語」ということについては、ジョン・オカダの日系の「ノーノ―ボーイ」の話がすこぶる面白い。ジョン・オカダの未亡人が「ノーノ―ボーイ」の原稿をカリフォルニア大学に寄付しようと持参したら、グッドイングリッシュじゃないと、拒否されたという。怒った未亡人は原稿を燃やしてしまう。
(小田) それから数年たってから、日系あるいはアジア系アメリカ人の若い作家たちの集団が彼を発見して、未亡人のところに駆けつけると、「あなた方来るのが遅すぎた」と未亡人が言う。その時に彼らは言った。何がグッド・イングリッシュかと。われわれが話し、書き、しゃべり呼吸してきたイングリッシュこそグッド・イングリッシュじゃないか。誰が一体グッド・イングリッシュをきめるのだと。そんなこともあってアジア系アメリカ人の作家が二つに分かれたでしょう。アンソロジーが二つあるわけです。一つはグッド・イングリッシュ的なやつと、そんなのくそくらえというやつと。私は、くそくらえ派なんです。日本語についても。(p.44)
これは、ラテン語やギリシャ語が、俗語に変化していく言語発生過程の話と重なるのではないか*1。
ぼくらとしては、いわゆるジャパニーズ・イングリッシュじゃなくて、ある意味の規範になるような日本英語をつくるべきではないかと思っているのです。(略)グッド・イングリッシュを廃止するというのではなくて、くそくらえ派もいるし、グッド・イングリッシュもある。そういう基本的な広がりのあるものをつくったほうがいいんじゃないか。
ある意味ではへんな話だけれども、日本人はもっと英語に寄与したらいいと思うのです。たとえば在日朝鮮人の書く日本語というのは、なかなか豐かですよ。
小田氏は、以上のように述べて、「だから私は、日本の英語教師たちが、あるいは英語を考える人たちが考えて、おもしろい教科書をつくったらどうかと思うのです」と述べている。
そして、専門家はちゃんと英語を学んだほうがよいということを前提にして、中学・高校の英語教育は、基本的なことをおさえて、先の日本英語を基本として確立することだとして「私が主張したいことは、まず日本英語をちゃんと確立する。日本人全部が義務教育を受けて、三年間やるのだったら、最低の日本英語を身につけるということは、この世の中で非常にいいことだと思うのです」と述べている。「それ以上の英語は、専門家がちゃんとやれ」と。
さらに、視点が少し違うけれど、小田氏は、「ぼくは英語を学ぶ目的は道具としてじゃなくて、自分の思考の幅を広げるということに徹したらいいんじゃないかと思う」と述べている。
したがって先の教科書づくりについても、「私が教科書を作るとすれば、中学・高校での基本的な教育はね、まず思考の幅を広げるものに徹する。道具の段階はその次です」と述べ「極端な話をすれば、私たちが教科書を作るのだったら、日本人の書いた英語とか、非英米人の書いた英語、それを集めた教科書を作った方が、はるかに意味があるという気がする」と述べている。
小田氏の体験にもとづく英語教育論はすこぶるおもしろい。ひとつには、主体性を奪われてはならないということなのだろう。大変参考になる。
他にも引用したくなる話はたくさんあるけれど、今日はこの辺でやめておく。